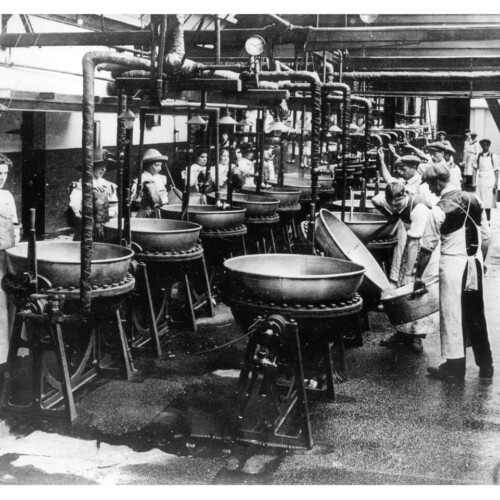イギリスの夏のお楽しみ、音楽祭Proms(プロムス)とは?
ロンドンの夏の風物詩、BBC Proms(通称プロムス)。世界最大規模のクラシック音楽祭であり、毎年7月から9月にかけて、ロイヤル・アルバート・ホールを中心に繰り広げられます。英国人のみならず、世界中の人々に愛される大人気の音楽祭です。普段は「敷居が高い」と感じられがちなクラシック音楽も、この時期だけは身近に、そしてよりカジュアルに楽しむことができる――それがプロムスの魅力です。

プロムスの成り立ち
プロムスはその規模と文化的な背景から、イギリスの夏を象徴するイベントとなっています。もともとは1895年、当時できたばかりだったクイーンズホールの支配人だったロバート・ニューマンが考案した、「より広い聴衆に、安い価格で、気楽に参加できる演奏会を」というプロジェクトが発端でした。そのころすでに指揮者やオルガン奏者として音楽界に頭角を現していたヘンリー・ウッドにニューマンが声をかけ、オーケストラの指揮者のポジションを与えて第1回プロムスを託しました。以後約50年、亡くなる年までウッドはプロムスの指揮者、リーダーとして活躍しました。

プロムスの由来、「Promenade(プロムナード)」とは、フランス語で「散歩」の意味。オーディエンスが立ちながら自由に音楽を楽しむスタイルを取っており、現在も全員立ちっぱなしのアリーナ席などにその名残が見えます。そして昔はなんと演奏を聴きながらの飲食、喫煙も許されていたそうです。
その後1927年にBBC(英国放送協会)がプロムスの主催を引き継ぎ、演奏会を放送できるようになったおかげでロンドンのみならず全国にファンが広がり、音楽祭として定着しました。

クラシックの名曲はもちろん、現代の作曲家による新作の発表など、多彩なプログラムが毎年提供され、老舗の音楽ファンから新しい世代まで、幅広い層に愛されています。
今年(2025年)は7月18日から9月13日まで、約2ヶ月の間に80以上のコンサートがロイヤル・アルバート・ホールを中心に繰り広げられています。
(公式サイトはこちら)

プロムスのハイライト、Last Night of the Proms
特に注目すべきは、プロムスの最終日にあたる「Last Night of the Proms」(以下 Last Night)。この日のコンサートの前半は毎年様々な作品が演奏されますが、後半は愛国心あふれる楽曲が続き熱狂的に盛り上がる、プロムスのまさにハイライトです。
ではLast Night お約束の曲を見て、そして聴いていきましょう。
アーン作曲「ルール・ブリタニア」Rule Britannia
まずはこちら、2016年の様子をご覧下さい。
イギリスを擬人化した女神ブリタニアが世界を支配するであろうと高らかに歌い上げる作品です。後半、聴衆も参加して繰り返し歌われる部分は、
Rule Britannia! 統べよ、ブリタニア!
Britannia, rule the waves. 大海原を統治せよ
Britons never never never shall be slaves. ブリトンの民は 断じて 断じて 断じて 奴隷とはならじ
という歌詞(訳詞は日本語wikipediaより)。このあとご紹介する歌も皆、現代の感覚だと「大英帝国万歳」感が強すぎて気になる方もいるかもしれません。が、愛国心に満ち満ちたLast Night、オーケストラこそBBC交響楽団ですが、指揮者やソリストは外国人であることも多いのです(もちろんイギリス人音楽家だけで毎年は賄えないという現実的な理由はありますが)。
さらにはこの動画の年のようにソリストの出身国の衣装でもOK(テノール歌手ファン・ディエゴ・フローレスはペルーの出身で、この衣装はペルーのものだそう)。いかにもイギリス的な寛容さが良いなと思います。
エルガー作曲「威風堂々(Pomp and Circumstance)」
さて続いては、エルガー作曲「威風堂々(Pomp and Circumstance)」です。
日本でも有名な曲なので、メロディはご存じの方も多いことでしょう。
では2014年の様子をどうぞ。
この年の指揮者はサカリ・オラモ(BBC交響楽団の首席指揮者)。フィンランド人ですが、ジャケットの中に着ているベスト(イギリス英語ならwaistcoat)は派手なユニオンジャックデザインで、衣装でも盛り上げています。
この動画は特に会場の雰囲気がよくわかると思います。ロイヤル・アルバート・ホールの広さ高さ、そして聴衆の盛り上がり。特にこの歌のときは立っている人たちがリズムに合わせて軽く膝を曲げ、ピョコピョコと動くのも特徴です。

日本では「威風堂々」のタイトルで知られるこの曲は、もともと6つの行進曲からなる作品の第1番です。1901年、リバプールでの初演の2日後にロンドンのプロムス会場で演奏されましたが、その時の指揮者、前述のヘンリー・ウッドの回顧によると「聴衆は立ち上がり、叫び、2度もアンコールがかかったほど」の大興奮だったそうです。
この名曲は当時の国王エドワード7世の耳にも入り、たいそうお気に召したそう。国王直々に「この曲に歌詞をつけてみたらどうか」とのご提案があって、A.C.ベンソンの詩を付けました。戴冠式用に作った歌なので、もちろん大英帝国万歳です。タイトルは Land of Hope and Glory、希望と栄光の国。自然と第2の国歌という位置づけとなり、現在に至ります。
歌詞と和訳はこちらの日本語wikipedia(2番の歌詞)をどうぞ。
パリー作曲(エルガー編)「エルサレム (Jerusalem)」
そしてこちらも毎年Last Nightのお約束、パリー作曲(エルガー編)「エルサレム (Jerusalem)」です。
元は1916年に作曲されたパリーによるオルガンと合唱のための作品が、エルガーの手によって管弦楽版に編曲、プロムスではこれを演奏しています。Last Nightではもちろんのこと、ラグビーなど国を代表するスポーツの場でも歌われることが多く、前述の「威風堂々」と同じく、こちらも「第2の国歌」と呼ばれています。この曲も、イギリス人でなくても感動的な音楽です。
歌詞はこちら 日本語wikipediaをどうぞ。
締めには国歌、そして「蛍の光」
そして最後には国歌 God save the King、続いて「蛍の光」Auld Lang Syne が演奏されます。
次の動画はLast Night のエンディング、2011年なので God save the Queen です。近年のプログラムには「蛍の光」も演奏曲目として入っていますが、この年は入っていなかったようでオーケストラの演奏はなく、自然発生的に聴衆が歌っています。
(エルサレム~国歌~蛍の光、と続きます。国歌からお聴きになりたい方は2分50秒あたりからどうぞ)
いかがでしたか?Last Nightのチケットを取るのは大変そうですが、もしプロムス期間中にロンドンにいらっしゃる方は、雰囲気だけでも味わいにロイヤル・アルバート・ホールに出かけてみられてはいかがでしょうか。
《ライター高島まきからのお知らせ》
ここで取り上げた歌を一緒に歌ってみませんか?
今年(2025年)10月頃にイギリスの歌を歌うイベントを計画中です。詳細が決まりましたら私のホームページや各種SNSでも告知しますが、メールでのご案内をご希望の方はこちらからメールアドレスをご登録ください。